
「うちの猫、また吐いてる…」
「元気はあるけど大丈夫?」
猫が吐く姿を見ると、飼い主としてはとても心配になりますよね。
猫はもともと吐きやすい動物ですが、吐く原因には毛玉などの生理的なものだけでなく、消化器の病気や中毒、ストレスなど、さまざまな可能性があります。
この記事では、
「猫が吐く理由」
「飼い主がとるべき対応」
「受診の目安」
まで、わかりやすく解説します。
愛猫の体調が気になる方や、突然の嘔吐で不安になっている方は、ぜひ最後までお読みください。
獣医師 阿部透
猫が吐く原因は?

猫が吐く原因は、生理的な反応によるものから病気に起因するものまでさまざまです。
飼い猫が吐く原因にどのような可能性があるかを知っておくと、いざという時にも慌てずに行動できます。
吐くのはなぜ?原因は?
猫はその身体的特徴から犬に比べて吐きやすく、健康面に問題がなくても吐くことがある動物です。
猫には毛づくろいをする習性があり、便と一緒に排出されなかった毛玉は、吐き出すことによって体の外に出されます。
食道の構造も犬よりも吐きやすくなっており、消化に時間がかかり食べ物が長く胃にとどまるため、フードを吐き戻しやすいと言われています。
猫が吐く原因には生理的なものと病的なものがあり、空腹や早食い・一気食いで吐くのは生理的な反応です。
猫の嘔吐の原因として考えられる病気は?
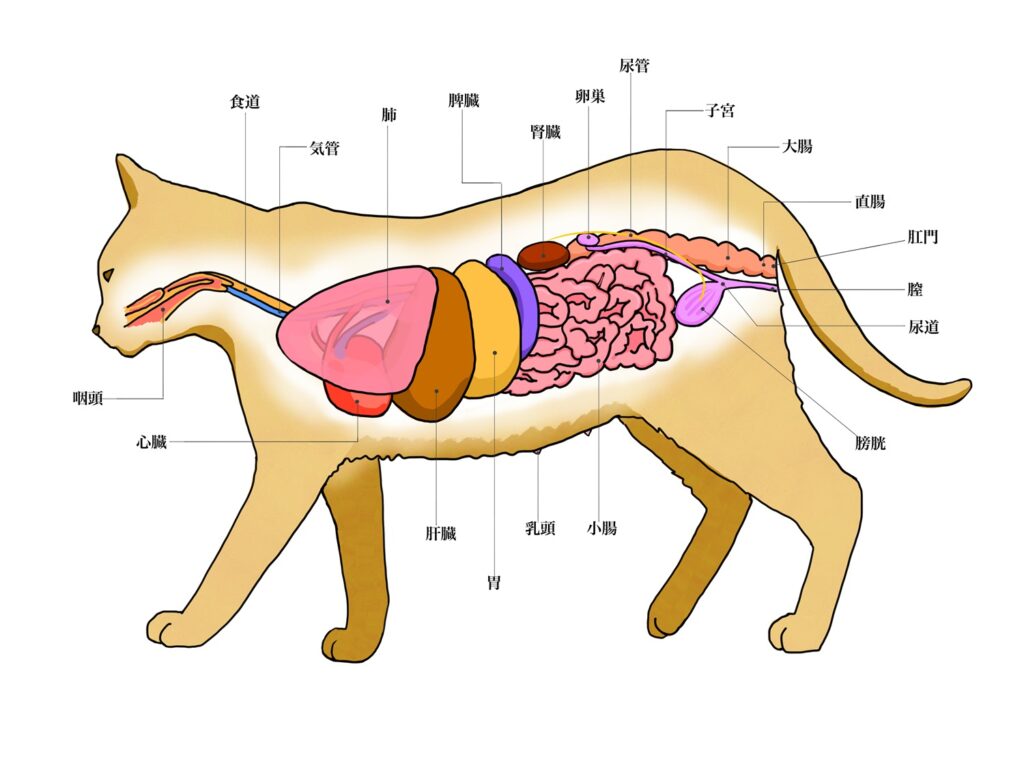
猫の嘔吐の原因として考えられる病気には、消化器系の病気をはじめ、代謝疾患や中毒、感染症などさまざまなものがあります。
1.消化器系による原因
もっとも多いのは消化器系の病気で、胃炎・腸炎・異物の誤飲・腫瘍・腸閉塞(ちょうへいそく)・便秘などです。
食べたものが胃や腸を通過できず、嘔吐が起こります。
2.代謝性疾患による原因
また、膵炎(すいえん)や肝機能障害・胆嚢炎(たんのうえん)・腹膜炎などの内臓疾患、甲状腺機能亢進症(こうじょうせんきのうこうしんしょう)・糖尿病・腎臓病といった代謝性疾患でも、吐き気や嘔吐が見られることがあります。
3.感染症による原因
感染症ではウイルス・細菌・寄生虫などが原因になることもあり、子猫では容態が急変しやすく注意が必要です。
4.中毒による原因
中毒を起こすものには、観葉植物・アロマ・洗剤・薬品・人の食べ物(チョコレートやタマネギ等)などがあります。
ストレスで吐くことはある?
猫は環境の変化を感じやすく、ストレスに弱い動物です。
人間にとってはささいなことでも、少しの生活環境の変化でも猫にとっては大きなストレスになり、吐くことがあります。
ストレスの原因を取り除く工夫や、安心できる生活環境を整えてあげることで改善が期待できます。
ストレスを軽減するサプリメントやフェロモン製剤などもあるので、それらの利用を検討してもよいかもしれません。
ストレスによる嘔吐は多くは一時的なものですが、長引いたり繰り返したりするようであれば、ほかの病気の可能性もあるので受診を検討しましょう。
吐いたときに飼い主がとるべき行動

飼い猫が吐いてしまった時に慌てずに済むように、飼い主がとるべき行動について確認していきましょう。
猫が吐いた!どうすればいい?【基本的な対処法】
とっさに飼い猫が吐いてしまい、生理的なものか病的なものかわからず対応に困ったときは、まず猫が吐いた状況や嘔吐物についてメモをしておきましょう。
嘔吐時に記録したい内容
・吐いた時間
・回数
・吐いたものの内容
・元気の有無
・吐く前後の猫の様子
・ご飯を食べてからの経過時間
・過去に誤食の有無
・下痢や食欲不振など他の消化器症状
上記の情報を記録しておくと、診断の助けになります。
▶チェックポイント‼
【Check1】
スマートフォンなどですぐに撮影できる状況であれば、吐いている様子や吐いたものを動画や写真などで撮影しておきましょう。
【Check2】
吐いたものが何かわからないときや、写真などで記録できない場合は、嘔吐物を保管しておきましょう。※ティッシュペーパーなど水分を吸ってしまうものにくるんでしまうと状態がわかりにくくなるため、ビニール袋やラップを利用するのがおすすめです。
病院で獣医師に説明するときに、吐いたものや吐いた時の様子の動画を見せると、診察がスムーズに進みやすくなります。猫の様子を注意深く観察し、次に解説する内容に当てはまる場合は、すぐに動物病院を受診しましょう。
猫の嘔吐でこんな症状が見られたらすぐ病院へ

猫が吐いたときには、緊急性が高いかを判断するために呼吸や意識に異常がないかをまず確認します。
呼吸が苦しそう、意識がぼんやりしている場合には、すぐに受診が必要です。
異物や有害物を飲み込んだ場合
異物を飲み込んだ可能性や、有害なものを摂取した可能性がある場合は、すぐに動物病院を受診してください。誤飲から3時間以内であれば、催吐処置によって体外に排出できる可能性があります。
▶チェックポイント‼
例外としてブドウ、レーズン、チョコレート、キシリトールなどのように胃に長く留まる食品は、3時間以上経過していても処置が検討されることがあります。
その他の症状
・嘔吐を1日に何度も繰り返す
・嘔吐が数日間続く
・吐いたものに血が混ざっている
・水も飲めずぐったりしている
・下痢や発熱などの症状もある
このような場合は緊急性が高いケースです。
特に子猫や高齢猫、持病がある猫では、症状が急激に悪化する場合もあります。飼い主目線で「いつもと違う」と感じたら、自己判断せず速やかに動物病院で診察を受けましょう。
受診時に獣医師へ伝えたい情報

【1】記録した情報の共有
受診時には、事前にメモしておいた内容(吐いた時間、回数、吐いたもの等)を獣医師に伝えます。
【2】かかりつけ動物病院以外の場合
かかりつけの動物病院以外を緊急で受診する場合には、これまでどんな病気にかかったことがあるか、飲んでいる薬があれば何の薬かを伝えます。
【3】薬の名前がわからない場合は
薬をそのまま持参して獣医師に見せましょう。
【4】健康診断結果・血液検査結果の情報
直近で健康診断や血液検査を実施していれば、その結果についても伝えてください。
【5】誤飲物
誤飲した可能性があるおもちゃなどがあれば、その残りを持参して獣医師に見せましょう。
【6】誤飲物が不明の場合
何を食べてしまったかわからない場合は、可能性のあるものを持っていってください。飲み込んだものの形がわかっていると、レントゲンやエコーなどの検査時や、その後の診断や処置の際に参考になります。
猫が吐いても様子を見ていい場合(自宅で様子見をしてよい例)

猫が吐いた場合、基本的には自己判断をせずに受診をしてください。
ただし、早食いで吐いたなどの生理的な反応の場合は、いつもと様子が変わらず元気があるかどうかを確認したうえで、様子を見ることもできます。
▶チェックポイント‼
数日様子を見て、何度も吐いている、だんだん元気がなくなってきたなど、変化があればすぐに受診してください。
吐きたそうにしていて吐けない場合

猫が吐きたそうにしているのに吐けず、苦しそうにしている場合は、すぐに受診しましょう。
異物や腫瘍など物理的な要因でうまく吐けない場合には、すぐに処置が必要です。
胃拡張捻転症候群(いかくちょう ねんてん しょうこうぐん)や腸閉塞(ちょうへいそく)など、緊急の手術が必要になるケースも。
▶チェックポイント‼
また、何度も吐いているせいで吐くものがない場合は、脱水を起こしているかもしれないので、受診して点滴などの処置が必要です。
吐いた「もの」や「色」

猫が吐いた原因を探るためには、吐いた内容物や色をよく確認する必要があります。
猫がよく吐くことがある内容物と、吐いたものの色から何がわかるかを見ていきましょう。
毛玉
毛づくろいで飲み込んだ毛が便と一緒に排出されず、胃の中に溜まると、不快感から毛玉を吐き出します。猫の習性なので緊急性は低いですが、毛玉が大きくなりすぎて吐き出せなくなると「毛球症」という病気になり、胃炎や通過障害の原因になる場合があります。
寄生虫
吐き出したものの中に動くものがいた場合、寄生虫の可能性があります。
猫の寄生虫にはいくつか種類がありますが、嘔吐した中に見られるのは、そうめんのように白く細長い見た目をした「猫回虫」の場合がほとんどです。駆虫薬で駆除する必要があり、受診が必要です。
異物
ヒモ類やおもちゃなどの異物を誤って飲み込んでしまった場合、異物が体内から排出されるまで繰り返し吐くことがあります。
命にかかわる可能性「すぐに受診を!」
異物は種類にかかわらず、消化管の閉塞や穿孔(せんこう)を引き起こし、命にかかわる可能性が高いため、自然に吐き出すのを待たず、すぐに受診してください。
ヒモ類は要注意!
特にヒモ類は、猫の舌がざらざらしているため遊んでいるうちに舌に引っかかり、意図せず飲み込んでしまうことがあります。ヒモは腸閉塞を起こしやすく、非常に危険です。普段から危険なものは猫の手の届く場所に置かないようにしましょう。
餌・キャットフード
食べたキャットフードをそのまま吐き出した場合は、早食いや一気食いの影響が考えられます。
早食い防止用の食器を使うなどの対策をすることで改善できる可能性があります。
また、病的な要因で、食道から胃に障害があるような異物、食道炎、胃腸炎、腫瘍、幽門狭窄(ゆうもんきょうさく)、巨大食道症などの可能性がないかどうかも注意が必要です。
茶色のどろどろとしたペースト状のもの
茶色のどろどろとしたペースト状のものは、キャットフードが消化された状態で吐き出されたものです。吐き出されたフードの消化状況から、どの器官で異常が起きたのか推測可能です。
・半分ほど消化が進んでいれば、胃
・ほぼ消化されている場合は、十二指腸などの腸管
などに問題がある可能性があります。
黄色い液体・泡
黄色い液体や泡は、空腹による胃酸過多や胆汁の逆流によるものです。
胆汁にはビリルビンという黄色い色素が含まれており、胆汁が胃に逆流して胃液と混ざって吐き出されます。
原因は?
食事の間隔が長すぎる、食事の回数が少ない可能性が考えられるので、食事のタイミングや回数を見直すことで改善する場合もあります。
受診の目安
食事の時間や回数を見直しても嘔吐が続く場合は、消化管の病気だけでなく、肝炎や腎臓病などの病気の可能性もあるので、受診を検討してください。繰り返し何度も吐く場合は緊急性が高いケースがあります。
水っぽい・無色透明、白い泡状のもの
透明または白い泡状のものを吐いた場合は、胃酸や飲み水の逆流によるものです。
ストレス状態や空腹時に胃酸過多になると、胃液を吐き出すことがあります。吐き戻す前に水を飲んでいると、胃液と一緒に水を吐き出すので、透明になります。
緑
緑色の液体を吐いた場合、その色の元は黄色の液体と同じく胆汁です。黄色よりも濃く見えるのは、胆汁の濃度や混ざる物質(胃内容物、猫草など)によるものです。
緊急性もあるので注意!
緑色の場合は、異物の誤飲や複数回続く嘔吐によって胆汁が多く逆流していることがあり、原因によっては緊急性が高いケースもあります。
受診の目安
短時間に何度も吐く、元気や食欲がない、異物誤食の疑いがある場合は、すぐに受診してください。
一方で、猫草を食べた直後に1回だけ緑色の液体を吐くような場合は、それほど心配のいらないケースもあります。
ピンク、赤~赤黒い
ピンク色や赤色の液体を吐いた場合、口や食道、胃などの消化管から出血している可能性があります。
【注意】鼻からもピンク色の液体
鼻からもピンク色の液体が出ている場合は「心臓性肺水腫」という病気の疑いがあるので、すぐに受診してください。
赤黒い液体の場合
赤黒い液体を吐いた場合は、消化管にできた腫瘍(猫ではリンパ腫が多い)や潰瘍、炎症などによる出血の可能性があります。赤黒い色の塊を吐き出した場合も、出血や腫瘍性病変が関与していることが多く、いずれも緊急性が高いため、すぐに受診してください。
吐く頻度や回数

猫が吐く頻度や回数によっても受診の目安は異なります。
ときどき吐く程度で、元気があれば様子を見ても問題ない場合もありますが、吐く頻度や回数が多い場合は注意が必要です。
毎日、何度も吐く場合
猫は毛玉やフードを吐き戻しやすい動物ですが、毎日何度も繰り返し吐くようなケースでは早めの受診を検討しましょう。
異物誤飲による腸閉塞や、消化器系の病気の可能性があり、様子を見ているうちに状態が悪化することも。
高齢の猫が何度も吐く場合には、慢性腎臓病も疑う必要があります。
1日に何度も吐く、嘔吐が何日も続くと脱水症状になることもあるので、注意が必要です。
どの程度続くのか
猫の嘔吐は、回数や食欲・元気の有無、下痢など他の消化器症状の有無によって受診の目安が変わります。もし1日1回程度の嘔吐で、他に症状がなく元気や食欲も保たれている場合は、2〜3日ほど様子を見てもよいケースもあります。
ただし、
• 嘔吐に加えて下痢や元気消失など他の症状がある
• 1日に何度も繰り返し吐く
• 嘔吐が3日以上続く
といった場合には、消化器系の病気や誤飲などの可能性があり、早めの受診が必要です。特に子猫や高齢猫は体力が少ないため、症状が進行しやすいので注意してください。
猫は自分で病院に行けないため、飼い主の早めの判断が重症化を防ぐポイントになります。
その他
突然の嘔吐と下痢は、猫にとって毒性のあるものを摂取したことによる中毒の可能性もあり、緊急性が高い症状です。
中毒症状では、発熱・けいれん・震えなどの症状が見られることもあります。
また、子猫が激しい嘔吐と水下痢をしている場合は、パルボウイルスに感染している可能性があるので、同居猫がいる場合にはすぐに隔離してください。
そのほかにも、尿道が結石で詰まり、尿道閉塞から尿毒症を起こしているケースなども考えられます。
いずれの場合も様子を見ても改善はしないので、すぐに受診を検討してください。
吐くタイミングやシーン

猫が吐くタイミングやシーンによっても、嘔吐の原因は異なります。
受診時に、吐いたタイミングやシーンを伝えられるように、記録を残しておきましょう。
朝や食事前
朝や食事の前に空腹で胃液を吐くような場合、ほかに症状がなく元気があれば、緊急性は低いと言えます。
食事のタイミングや量を調節することで改善できる場合もあるので、心配であれば獣医師に相談してみましょう。
食後すぐから数時間後
猫が食後すぐに吐いた場合は、早食いや一気食いが主な原因です。
吐いたあとも元気があり、様子がいつもと変わらないようであれば、そのまま様子を見てもよいでしょう。
ただし、毎食後いつも吐くようなケースでは病気の可能性もあるので、一度受診をおすすめします。
食後数時間たってから吐く場合は、胃から腸への食べ物の通過がうまくいっていない可能性があります。
胃の運動機能の低下や、幽門部(胃の出口)の狭窄、腫瘍や異物による通過障害などの可能性があり、受診が必要です。
季節や気候
季節や気候によっても吐きやすい時期があります。
毛が生え変わる春と秋は抜け毛が多くなるので、毛玉を吐く回数も多くなります。
特に長毛種は毛量も多いので、こまめにブラッシングをするなどの対策が必要です。
また、夏の暑い時期に猫が吐いている場合には、熱中症の可能性があります。
呼吸が荒く、ぐったりしている場合には、すぐに受診しましょう。
点滴後に吐く
猫が点滴(皮下輸液や静脈輸液)の後に吐くことがあります。
原因は一つではなく、もともとの病気や体調不良、処置によるストレスが関係している場合もあります。まれに、過剰な水分補給や体内の電解質バランスの変化、投与した薬剤への過敏反応が原因となることもあります。
点滴後に嘔吐が見られた場合は、自己判断せず、症状や経過を記録して早めに獣医師に相談してください。
避妊手術や去勢手術後に吐く
手術に使われる全身麻酔は、覚醒後に吐き気を引き起こすことがあり、避妊手術や去勢手術などのあとに吐く場合、麻酔の影響が疑われます。
麻酔の代謝には術後数時間から半日ほどかかり、その後は吐き気もおさまります。
また手術前は食事を与えられていないので、空腹で白い泡や胃液を吐くケースも。
長時間絶食していたあとに急に食べると胃がびっくりして吐くことがあるので、少量ずつ与えるなどの工夫をしてください。
その他
猫がトイレで排便時に吐く場合、便秘が原因の場合があります。
便秘気味で便が硬いと、排便時に強くいきんだ時に、腹部の圧力が胃を刺激して吐くことがあります。
便秘が長引くと、結腸が拡張して排便困難となる『巨大結腸症』を発症するリスクがあるため、排便時の嘔吐が続く場合には、受診を検討しましょう。
猫の嘔吐に関する疑問

Q:何歳からよく吐くようになるの?
A:毛玉を吐く行動は、猫の毛づくろいによって飲み込まれた被毛を排出するための自然な現象です。換毛期(春や秋)、被毛が増える成猫期、特に長毛種では毛玉を吐く頻度が高くなる傾向があります。一般的には、1 〜 2週間に1回程度吐くことは珍しくありません。ただし、頻度が多すぎる場合や、吐いた後の体調に不安があるときは早めに獣医師に相談しましょう。
Q:毛玉を吐く頻度はどのくらい?
A:健康な猫でも、毛玉を月に1~2回程度吐くことはよくあります。ただし、頻度が週に何度もある、毎日のように続くなどの場合は、胃腸の異常や毛球症のリスクもあるため、獣医師への相談をおすすめします。
Q:毛玉を吐く量は?
A:毛玉の量には個体差がありますが、直径2〜5cmほどの細長い形状で吐き出されることが多いです。まれに大きな毛玉を吐く場合もありますが、頻繁に大量の毛を吐くようであれば、毛球症の前兆である可能性もあるため、一度診察を受けてみてください。
Q:毎日吐いてるけど大丈夫?
A:毎日のように吐くのは、毛玉だけが原因とは限りません。消化器の病気や誤飲、慢性的な炎症などの可能性も考えられます。元気や食欲があるかどうかも含めて、状態をよく観察し、早めに動物病院を受診することをおすすめします。
Q:吐く前兆はある?
A:吐く前には、落ち着きがなくなる、喉を鳴らすような動作をする、床を舐める、よだれを垂らす、吐く仕草(えづき)をするなどの前兆が見られることがあります。こうしたサインに気づけると、吐く原因を記録したり、吐いた物を確認しやすくなります。
Q:吐く毛玉の色が、茶色・黄色・緑だったりするけど大丈夫?
A:毛玉に混ざる胃液や胆汁の影響で、吐いた毛玉の色が茶色・黄色・緑色になることはあります。茶色や黄色は比較的一般的ですが、緑色の場合は胆汁の過剰分泌や消化器疾患の可能性があるため注意が必要です。色やにおいがいつもと違う、頻繁に見られるなどの場合は、一度診察を受けてみましょう。
まとめ

猫はとてもデリケートな動物で、ちょっとした体調の変化や環境の変化でも吐いてしまうことがあります。毛玉を吐くのは猫の自然な習性のひとつですが、回数が多い、吐いたものの色がおかしい、元気や食欲がないなどの症状がある場合には、重大な病気が隠れている可能性もあります。
猫の嘔吐は、命に関わるサインであることもあるため、「様子を見ても大丈夫かな…」と迷った時こそ、早めの受診が大切です。
「いつもと違うかも」と感じたら、お気軽にご相談ください。飼い主さまと大切な家族である猫ちゃんが、安心して過ごせる毎日をサポートいたします。
当院について

愛猫の「いつもと違う様子」に少しでも不安を感じたら、東中野アック動物医療センターへご相談ください。
当院は猫の病気に詳しい獣医師が在籍し、丁寧なカウンセリングと総合診療・専門医療を兼ね備えた体制で、飼い主さまと一緒に原因を探ります。
土日祝も診療対応、内視鏡などの高度検査も可能です。
中野区・杉並区・新宿区エリアからのアクセスも良好。
大切なご家族の健康を守るために、どうぞお気軽にご来院ください。


